rust: Rustがんばろう 20日目
10章の最後
まとめのところだが、記憶に残っていない。。。
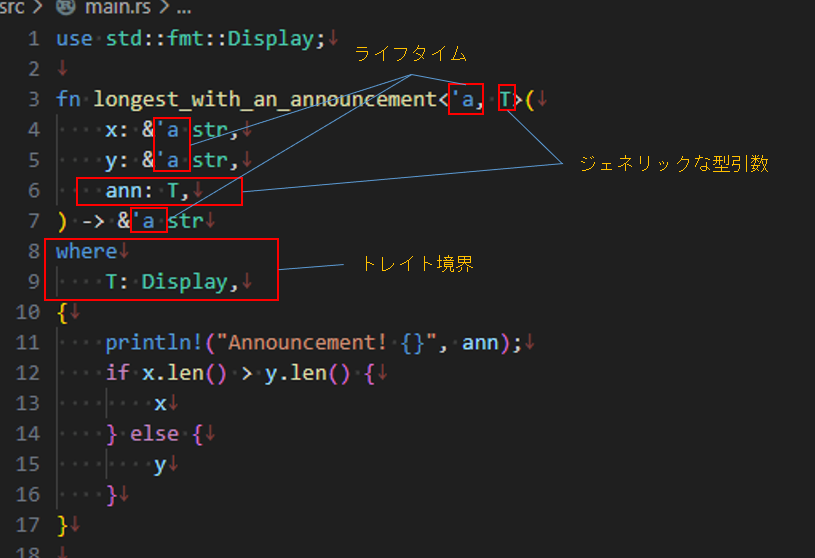
この3つをまとめた章で説明するところが Rust の言語的な特徴を表しているのかもしれない。
もう記憶から抜けているので再履修しているところだが、「トレイト」がわかりづらい。
「他の言語のインターフェースに似ている」という注釈がありがたい。
インターフェースというと、だいたいオブジェクト指向がどうのこうのという説明があるものだけど、あまりここでは触れていないように見えた。
トレイトを説明するためにはジェネリックのことを先に話しておかないとなあ、ああ書き方に近いものがあるしライフタイムもその流れで説明しておくか、という感じだろうか。
3つとも記載する箇所がコード本体ではなくシグネイチャとかそういう部分なのも特徴的かもしれない。
こういうのを覚えるのが面倒だとは思ってしまうのだが、C言語はこの辺が実装者任せになっているがために苦労することからすると、 記述での制約によってコンパイラがチェックできる箇所を増やすという方向性になるのか。
トレイト境界、か
しかし・・・”トレイト境界”が何を指しているのかよくわからない。
過去の私もやはり同じことを気にしている。
私としては interface という名称にしてほしかった。
どうせどの言語でも interface の内容は違っているのだから「ああ Rust の interface はこういう感じね」と割り切ったんじゃないかなあ。どうかなあ。
まあ、仮定の話をしても仕方ない。
writer: hiro99ma